The Man of The Month
「今月生まれのこの人」の “心にきざむ言葉”

「敵もあれば、味方もあるといった張りがなければ・・・」 岡本綺堂
岡本 綺堂
おかもと・きどう
(1872年10月15日生まれ)
シャーロック・ホームズに
刺激を受ける
岡本綺堂は、『半七捕物帳』シリーズを書き、日本の捕物帳小説の幕を開いた人です。
明治時代から昭和初期にかけて活躍した劇作家・岡本綺堂は、明治5年(1872年)に東京・芝高輪(現在の東京都港区高輪)に生まれています。
高校卒業後、東京日日新聞や中央新聞などで新聞記者活動をしながら、劇評や新聞小説を書き、しだいに作家活動に専念していくようになっていったのです。
新歌舞伎の脚本となる戯作『修善寺物語』、『番町皿屋敷』などを著した後、岡本綺堂の名を一段と高めたのは、日本で最初の捕物帳小説となる『半七捕物帳』シリーズを書いたことでした。
江戸時代を舞台に、「岡っ引き・半七」が難事件・珍事件に挑み、その英知と行動によって事件を解明していくストーリーは、「謎解きの面白さ」をはじめて読者に提供した小説として、現代でも高い評価を得ています。
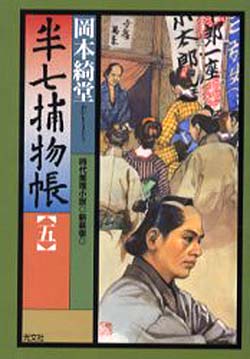
岡本綺堂はこう説明しています。
「コナン・ドイルが生み出したシャーロック・ホームズものを読んで、私自身の中にメラメラと探偵小説への興味が沸きはじめた。西洋の模倣に陥らないように、時代を江戸に戻し、江戸の情緒・風俗・習慣を書き込んだ」いわば、岡っ引き・半七は日本のシャーロック・ホームズとして誕生したのです。
外交官であった父を持つ岡本綺堂は、その英語力をいかして、早くから英文の「シャーロック・ホームズ」を読みこなしていたのです。
いつも洋書を探し、面白そうな本を買い求める岡本綺堂の名は、丸善の社史にも登場しているそうです。
「神田三河町の半七」に
みな引き込まれていく
半七捕物帳は、技法としても「青年新聞記者である作者が、明治20年代に、かつての江戸の岡っ引きをしていたという半七老人と、浅草で知り合い、半七老人が関わった珍事件・難事件を、茶飲話として聞きだしていく」という、斬新な設定です。
69篇のシリーズ第一作目にあたる『半七捕物帳・お文の魂』には、半七の風貌がこう記されています。
「縞の着物に縞の羽織を着て、誰の眼にも生地の堅気とみえる町人風であった。色の浅黒い、鼻の高い、芸人かなんぞのように表情に富んだ眼を持っているのが、彼の細長い顔の著しい特徴であった。・・・・」
月刊誌『文藝倶楽部』の連載小説として掲載された半七捕物帳は、読者の人気を集めます。
「半七」は、綺堂がフィクションで生み出した人物にもかかわらず、巷には「実は私は、半七の縁戚なんです」という人や、「半七と同じ長屋の生まれ」と真顔で語る人が出てきたりしたのです。
後に、多くの著名作家が、「綺堂・半七シリーズ」の愛読者になっています。松本清張、山田風太郎、森村誠一、宮部みゆき・・・・・・。
みな、人の持つ観察眼と知恵・カンによって、犯人にたどり着いていく「神田三河町の半七」に引き込まれていったのです。
岡っ引きには、強力な捜査権限があるわけでもなく、科学的な捜査方法もない時代の話です。
シリーズ物にありがちな、作品ごとの大きなばらつきがなく、どの作品もレベルが高く、しかも、怪談あり、サスペンスあり、本格的推理あり・・・で、毎回、趣向が違った新鮮さに富んでいます。
そこに、情緒、風俗、人情がからんで、「ページをめくる手が止まらなくなる」というファンも多いのです。
徒党を嫌い、妥協をせず
創作活動一直線に徹す
岡本綺堂は、折り目正しいことをモットーにしており、「筋を通す」ということに関しては決して妥協しない人だったようです。
劇作家としても、川上音二郎や市川左団次らの役者・歌舞伎役者のために多くの作品を書いていますが、俳優と私的な付き合いはいっさいせず、新作上演のときも舞台稽古に立ち会って、初日を見るだけで、つねに一定の距離を保っていたのです。
「誰からもいい人だと褒められるようではダメだ。敵もあれば、味方もある、といった張りがなければ・・・」と綺堂は語っています。
その信条は「一身のほかに味方なし」で、自分自身にも甘えないという剛毅なものだったのです。
「私は自宅にいる場合、飯を食うときの他は、机の前を離れたことはありません。読書や原稿書きだけでなく、ただボンヤリしているときでも必ず机の前に座っています。鳥で言えば『止まり木』のようなものです」
身近にいた人の目からも、綺堂の机の上は「筆一本、紙一枚も散らかっておらず、チリひとつないほどだった」というほどで、「孤独を楽しむ姿があった」そうです。
酒は飲まず、旅嫌い、会合嫌い、徒党が嫌い、スポーツ・ギャンブルが嫌い、骨董集めも嫌い、イデオロギーも嫌い・・・・・・。
ただ、愚直に創作に明け暮れる人生を岡本綺堂は送ったのです。

