The Man of The Month
「今月生まれのこの人」の “心にきざむ言葉”

「生業には貴賤はないが、生き方には貴賤があるねぇ」 勝海舟
勝 海舟
かつ・かいしゅう
(1823年1月30日生まれ)
幕末から明治にかけての激しい流れの中で、勝海舟が「新たな時代」を拓くために果たした役割は、とても重要なものでした。その思想は坂本竜馬ら多くの革新者に大きな影響を与え、交渉人として勝海舟にしかできない役を演じてきたのです。
西郷隆盛との三日間会談
江戸城の「無血開城」を実現させる
勝海舟は戦乱の表舞台に立つことはありませんでしたが、歴史書の中でドラマチックに語られるのは「「江戸城の無血開城」に至る「勝海舟・西郷隆盛の三日間会談」でしょう。

1868年、薩摩・長州の連合軍は圧倒的な兵力優位を背景に、鳥羽伏見の戦いにも勝利し、朝廷からは“錦の御旗”を授けられた「官軍(新政府軍)」は、いよいよ徳川家の本丸である「江戸」の地に迫っていきます。
西郷隆盛らに率いられ、勢いに乗って3月15日に「江戸城総攻撃」を決めていたのです。
大都会・江戸が戦乱の地と化し、その争いのために一般の庶民を含めて、多数の犠牲者が出ることが予想されました。
徳川家の家職である陸軍総裁の要職にあった勝海舟は、官軍が静岡の駿府城まで迫ってくると、全くの劣勢でも「あくまでも徹底抗戦」を主張する一派に対して、「早期停戦と江戸城の無血開城」を主張します。
それは江戸市民150万人を戦火から守り、新しい時代の到来を冷静に分析した、勝海舟の大きな決断でもあったのです。
「日本人同士が、血を流さないためにはどうしたらいいか」
3月13日に、勝海舟は従者一人だけを連れ、西郷隆盛の待つ薩摩屋敷(現在の田町)へ向かったのでした。
勝海舟、46歳の時です。
すでに、勝海舟が使者として送った山岡鉄舟が行っていた事前交渉では、西郷側から、「徳川慶喜の身柄を備前藩に預けること、軍艦・武器などのすべて引渡し、関係者の険しい処罰」などきびしい条件が付きつけられていました。
勝海舟と西郷隆盛との交渉は3日間に及びました。
「徳川慶喜を備前藩に預ける」という条件は、水戸に隠居して謹慎するという内容に改正させましたが、その他の条件は、ほとんど官軍側の要求をのまざるを得ません。
そして、勝海舟は西郷隆盛に「江戸城の無血開城」を約束し、西郷から「血気盛んな官軍軍勢を抑えること」「総攻撃の中止」の約束を取り付けたのです。

西郷隆盛と勝海舟の交渉(「西郷隆盛・勝海舟の会談の碑」より)
もし、江戸が戦火にまみれていたら…
日本が諸外国の支配下に置かれるケースも予想された
勝海舟はその交渉が「決裂」するかも知れないことも予測していました。
品川沖には榎本武楊軍が率いる幕府軍艦を配置し、万一の場合には「ゲリラ戦」を仕掛け、官軍を混乱させ、房総の大小の船をすべて隅田川の河口に集め、江戸市民を避難させる準備を行っていたのです。
まさに西郷との交渉は「崖っぷち」に立たされていた中での交渉だったのです。
会談の終了後、西郷隆盛は藩邸の外まで出て、勝海舟を見送った、と言われています。
では、「江戸城の無血開城」はどのような意味を持つのでしょうか?
まず、幕府軍も江戸城を拠点に徹底抗戦の意を構えていましたから、戦欄はかなり長引き、明治維新も相当に遅れたと考えられます。
同時に、江戸の地が戦乱で荒れ果て、その後、日本の首都としての機能が果たせる状態になったかは疑問です。
そして、何より戦火の広がりに乗じて、虎視眈々と権益の拡大を狙っていた英国をはじめとする諸外国の介入は確実に広がっていたことでしょう。
ともかく江戸城の無血開城は決まり、江戸の時代が終わり、明治維新の幕が開いていったのです。
のちのち、勝海舟はその生涯を振り返り、出会った中でその背筋が凍るような大人物として、横井小楠(儒学者で現実的開国論を説く)と西郷南洲(隆盛)の二人を上げています。
「小楠の臨機応変はただ者ではなく、西郷南洲(隆盛)はともかく大胆臓と大誠意が破格」と評しています。

西郷南洲(隆盛)
ちなみに、坂本竜馬は西郷隆盛を評して「大きく叩けば大きく鳴り、小さく叩けば小さく鳴る」と言ったのですが、勝海舟はこの評にうなづき、「評するも人、評されるも人」と話したそうです。
ペリー来航時の「上申書」が評価され
幕府内での地位を高める
勝海舟は文政6年(1823年)1月30日に本所亀沢町に生まれています。現在の「東京都墨田区両国」あたりです。
海舟が生まれたのは貧しい下級旗本の家で、父は勝小吉、母はのぶ、勝海舟は幼名「麟太郎(りんたろう)」と名付けられています。
あまりイメージには出てきませんが、勝海舟は13歳のころから島田虎之助の門下生として「直真影流」を学び、剣術の面でも免許皆伝の腕前を持っていました。
また、23歳のころからは、永井青崖について「蘭学」を学び、蘭和辞書である『ズーフ・ハルマ』を1年かけて筆写し、蘭学に精通したことがのちの世界観に大きな影響を与えることになるのです。
そんな時、日本全体を揺るがす事件が起こります。浦賀沖合に「ペリー」が4隻の軍艦を率いて来航したのです。
ペリーの強硬な要求に対し、徳川家は大名・幕臣から対策・意見を募るのですが、その大半は単なる「打ち払い論」か「穏便に」というものでした。
それらに対し、勝海舟が挙げた意見書は「人材を登用し、広く意見を吸い上げ、堅固な船舶を建造し、ロシア・清国・朝鮮とも交易、江戸の防備を固め、火器・武器を充実させること」など具体的なものでした。
この上申書が幕府老中の目に留まり、勝海舟は小普請の役から、下田取締掛手付を命ぜられ、次は長崎での海軍伝習生幹部、江戸に帰った際には「軍艦操練所教授方頭取」にまで出世していました。
咸臨丸の艦長として「新しい世界」を感じ
封建体制の限界を知る
万延元年(1860年)、38歳の時には、咸臨丸の艦長として日本と米国・サンフランシスコとの間を往復。この咸臨丸に福沢諭吉、ジョン万次郎らも乗り込んでいたことはよく知られています。

「咸臨丸」で米国・サンフランシスコへ向かう。
そして帰国後は軍艦奉行として『神戸海軍操練所』の建設と運営に奔走。そこには諸藩から「新たな時代」を作ろうとする志のある志士が集まり、坂本竜馬、陸奥宗光らもその一員でした。このころの勝海舟の胸中には、すでに日本とはまるで違う世界の在り方を見て、「幕藩体制」による封建政治ではこの先の世界の荒波を生き抜くことは不可能だと感じ取っていたのでしょう。
大政奉還、江戸城の無血開城、明治維新を迎えた後、勝海舟は旧幕臣の代表格として外務大丞、兵部大丞、参議兼海軍卿、元老院議官、枢密顧問官を歴任しており、「伯爵」の位も授けられています。しかし、実際には、求められた役職に応じただけで、長く役職にとどまることはなく、中央政府で自らの思いを積極的に実現させようという動きとは少し違っていました。

明治元年、海軍奉行時代。右から3人目の立っているのが勝海舟
生来の「おしゃべり好き」だが、
福沢諭吉とは「相容れず」
明治8年の元老院議官の職を最後に、みずから明治政府の職からは離れますが、勝海舟はとにかくおしゃべり好きで、著作も『亡友帖』『断腸の記』『吹塵録』など何冊も残しています。
赤坂・氷川に住み、政府の要人が相談に来れば自説をこんこんと話し、新聞記者がたびたび訪れくれば、海舟は時の経つのも忘れ、よもやま話や回顧談をおもしろおかしく話して聞かせていたのです。
「世人は首を回すことは知っている。回して周囲に何があるか、時勢はどうかを見極めることはできる。だが、もう少し首を上にのばし、前途を見ることを覚えなければならない」
「世の中に無神経ほど強いものはない」
「生業には貴賤はないが、生き方には貴賤があるねぇ」
勝海舟の言葉には独特のアイロニーやウィットが含まれています。
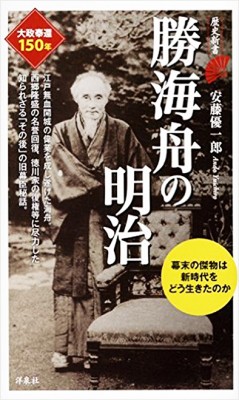
『勝海舟の明治』(祥泉社・歴史新書)の表紙より
「人の一生には“炎の時”と“灰の時”があり、灰の時には何をやっても上手くいかない。そんな時は何もやらないのがいちばんいい」
「時勢の変わり目というのは妙なもので、人物の値打ちががらりと変わってくるよ」
ただし、勝海舟と福沢諭吉との関係では、二人とも咸臨丸で新たな世界に目を開かされたはずなのですが、その思想と行動は、あまり交わることなく、生涯、平行線をたどっていたようです。
福沢諭吉は、大政奉還後、官職には就かず、その著作『瘠我慢(やせがまん)の説』の中では、「江戸城の無血引渡しは、旧主家を売って、新政府の顕営の地位を買ったようなもの」と評し、維新後も政府内の職を歴任した海舟の行動を批判しています。
また、勝海舟のほうは、慶応義塾の設立ために資金作りに奔走する福沢諭吉を「(学者然としながら)株などもいじって金儲けに走っている商売人みたい」と批判しています。
日本が江戸から明治という激動の変化・転換を遂げていく中で、先を読み、交渉といった稀有な役割を演じた勝海舟という人物を、歴史の中で軽視することはできないでしょう。
明治32年(1899年)1月19日、勝海舟は間もなく76歳となる日に、脳充血で息を引き取っています。
海舟が発した最後の言葉は「コレデオシマイ」というものでした。

東京墨田区に建っている勝海舟の銅像
勝海舟の墓は、別邸のあった東京大田区洗足池公園の中にあります。また、勝海舟の若き日をしのばせる銅像は東京都墨田区に建っています。
参考:『勝海舟のすべて』(小西四郎・編 新人物往来社)

