The Man of The Month
「今月生まれのこの人」の “心にきざむ言葉”

「日本人が口ずさめる、新しい歌を!」 滝廉太郎
滝 廉太郎
たき れんたろう
(1879年8月24日生まれ)
あまりにも短すぎる生涯の中で
天才作曲家が目指したもの
作曲家・滝廉太郎は1879年(明治12年)年8月、東京に生まれています。父は明治政府に勤める役人でしたが、その関係で東京から横浜・富山・大分と、目まぐるしく居を移すことになったのです。
小学校時代から成績優秀だった廉太郎は、大分・竹田の高等小学校時代に、音楽教師の影響で音楽に興味を持ち始め、たまたま学校にあったオルガンを弾いていたそうです。
音楽の道に進む決心をした廉太郎は、15歳の時に義兄を頼って上京。「東京音楽学校(現在の東京芸術大学)」を目指すのです。
最年少で仮入学試験に合格。本試験にも合格し、廉太郎は順調なステップを踏んでいきます。音楽の天才的な才能は高く評価され、大学卒業後もすぐに音楽講師の役割を担い、21歳のときに、文部省から西洋音楽の本場、ドイツへ留学する辞令が届いたのですが、あまりに廉太郎の才能が豊かだったために、「留学するのを1年先に延ばして欲しい」という学校の要請があったほどでした。
そして、この1年こそ、日本の音楽史に貴重な足跡を記す時間となったのです。
西洋音楽の輸入と模倣を中心として成り立っていた日本の音楽を、
「日本人が口ずさむことのできる音楽を、日本人の手で作りたい」。
廉太郎は1年間、この想いの実現に取り組んだのです。
廉太郎はまず「春夏秋冬」を表現した4曲で構成する合唱組曲を作曲します。
この『四季』と名付けた組曲は、『花』『納涼』『月』『雪』の4曲で構成されています。春をイメージする『花』は、よく知られている「春のうららの隅田川…」で始まるあの名曲なのです。
心に残る名曲を
次々と世に送り出す
滝廉太郎は、この組曲『四季』の緒言で、次のように記しています。
「近来音楽は、著しき進歩発達をなし、歌曲の作世に顕はれたるもの少しとせず。然れども、是等多くは通常音楽の普及伝播を旨とせる学校唱歌にして、之より程度の高きものは極めて少し、其稍高尚なるものに至りては、皆西洋の歌曲を採り、之が歌詞に代ふるに我歌詞を以てし、単に字句の数を割当るに止まるが故に、多くは原曲の妙味を害(そこな)ふに至る。(中略)此事を遺憾とするが故に、これ迄研究せし結果、即我歌詞に基きて作曲したるものゝ内、二三を公にし、以て此道に資する所あらんとす。幸に?先輩識者の是正を賜はるあらば、余の幸栄之に過ぎざるなり」
日本の人たちのための、新しい楽曲の創造へ、廉太郎の強い決意を見ることができます。
当時の文部省は、詩人から40編ほどの作詞を集め、これに作曲家が自由に作曲する形で中学唱歌を作るコンテストを行なっていました。
廉太郎は集まっていた40編の詩の中から3つを選び出し、曲を付けて応募したのです。
その3曲こそ『箱根八里』、『豊太閤』、『荒城の月』です。もちろん3曲とも入選し、わずかな期間で異なる作風の名曲をいっぺんに生み出した廉太郎の天才ぶりは広く世に知られることとなったのです。
それだけではありません。この同じ時期に、廉太郎は「幼稚園唱歌」の作曲にも取組み、『こいのぼり』、『、『お正月』、『桃太郎』、『鳩ポッポ』など次々と名曲を誕生させていくのです。まさに、天才・滝廉太郎の才能が爆発した時期だったと言えるでしょう。
「春高楼の花の宴 めぐる盃 影さして…」という歌い出しで知られる土井晩翠作詞・滝廉太郎作曲の『荒城の月』は、異分野の才気あふれる2人が生み出した名曲でした。
土井晩翠はこの詩を、戊辰戦争で被害を受けた会津若松の「鶴が城」と、故郷の仙台「青葉城」を重ね、思い浮かべて作ったと言っています。廉太郎は上京する前に住んでいた大分県・竹田の「岡城」、多感な時代を過ごした富山県の「富山城」を思い浮かべて作ったのでは…、と言われています。
荒城の月には、日本の様々な城の荒れた姿がイメージされているのです。
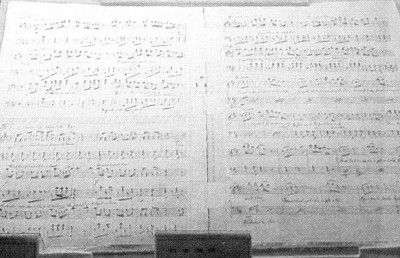
志し半ばでの夭折、
最期の曲「憾(うらみ)」に込められた思い
明治34年(1901年)の4月、22歳の廉太郎はドイツ・ライプチヒへ留学の途へ立ちます。 日本人音楽家としては二人目となる文部省外国(ヨーロッパ)留学生でした。
廉太郎は、胸躍らせ、音楽の先進の地でメンデルスゾーンが設立したというライプチヒ音楽院へ入学します。
しかし、順風だった天才作曲家に、ここからあまりに非情な運命が待ち受けていました。
欧州留学をはじめて半年後の11月に肺結核を発症。入院生活せざるを得ない状態になってしまうのです。
体調が思わしくない日々が続き、小康状態のときに、土井晩翠らの励ましを受けますが、そのときにはすでに廉太郎に死の影がさし始めていました。留学1年後、廉太郎は志し半ばで帰国。
病魔のとの闘いの中で、滝廉太郎は『別れの曲』、『水のゆくえ』、『荒磯の波』を作曲しています。
そして、明治34年(1903年)6月29日、療養先の大分で、わずか23歳と10ヵ月という、あまりにも短すぎる生涯の幕を閉じたのでした。
滝廉太郎の最期の作品は、『憾(うらみ)』と自ら名付けた壮絶なピアノ曲でした。
この「憾(うらみ)」という意味は、「恨み」という字が憎しみ、憤りを含んた感情を表しているのに対し、「憾(うらみ)」は「心のこり、残念に思う」気持ちを示すものです。
激しく胸を叩き、悲愴感をあふれさせた曲、『憾(うらみ)』は、廉太郎の無念の叫びだったのかもしれません。

